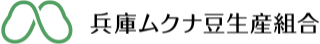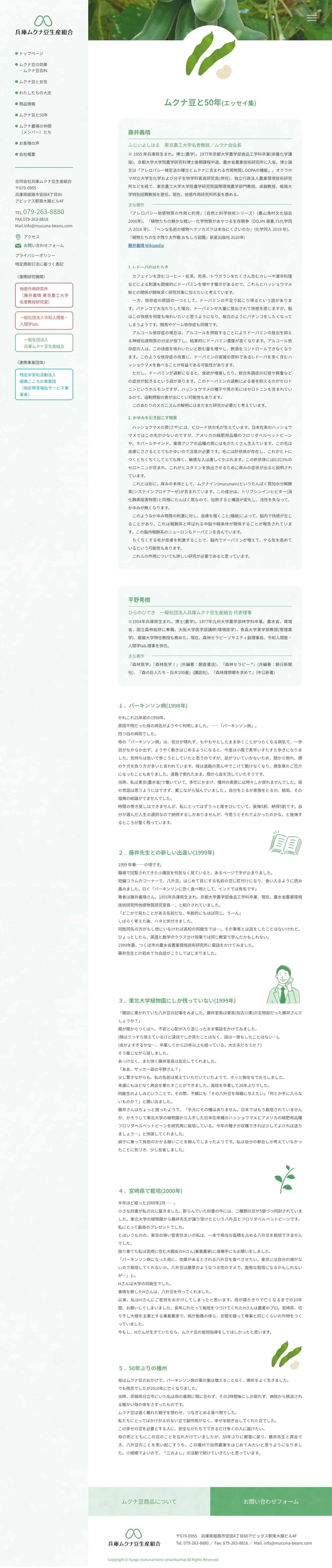6. 八升豆とムクナ豆
ムクナ豆(八升豆)の日本での栽培エリアは、商業的には南は沖縄から本州福島あたりまでと見ています。2年前、私は青森で栽培してみましたが、寒い5、6月が響いたのか、花は少ししか咲かず、豆はさほど穫れなかったです。北海道で栽培された方によると、翌年の種豆程度は確保できたそうです。
でも今年の暑さなら、日本中どこでも育つと思います。
市場ではムクナ豆と総称されていますが、「ムクナ」とは藤井義晴さんによると、属名のmucuna属のことで、ブラジルでの呼び名が「ムクナ」だったので、1984年以降、そう呼ぶことにしたそうです。これが一般化していきました。
現在、ムクナ豆として流通しているのは、国産の八升豆、フロリダベルベットビーンのほか、輸入物のインド産、ミヤンマー産、スリランカ産、ブラジル産、アフリカ産等のムクナ豆が混在しています。
弊社が扱っているムクナ豆は、純国産の「八升豆(ハッショウマメ)」で、西日本を中心にフツーに栽培されていた在来種です。幸運にも東北大学植物園に保存されていた八升豆を藤井先生が譲り受け、全国に広めました。江戸時代までは主に飢饉対策として作られていたといわれています。長崎・対馬に行ったとき、「このマメを知っている。栽培したことがある」という70代の女性の方がおられました。
明治以降、八升豆は急速に廃れていったのですが、理由として考えられるのは、①硬くて、靭性があり、加工しにくい。②花が一斉に咲かず、無限成長していくため収穫が一度で終わらない。作業が機械化しにくい。③美味しくない――ということではなかったでしょうか。
ムクナ豆の栽培が再開したのは、つい十数年間で、L-ドーパが着目されてからでした。

八升豆の方が皮は厚く、フロリダベルベットビーンほど痒くはならない。

緑色の生豆は畑で黄緑➡黄色➡黒色へと変化していきます。