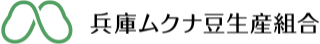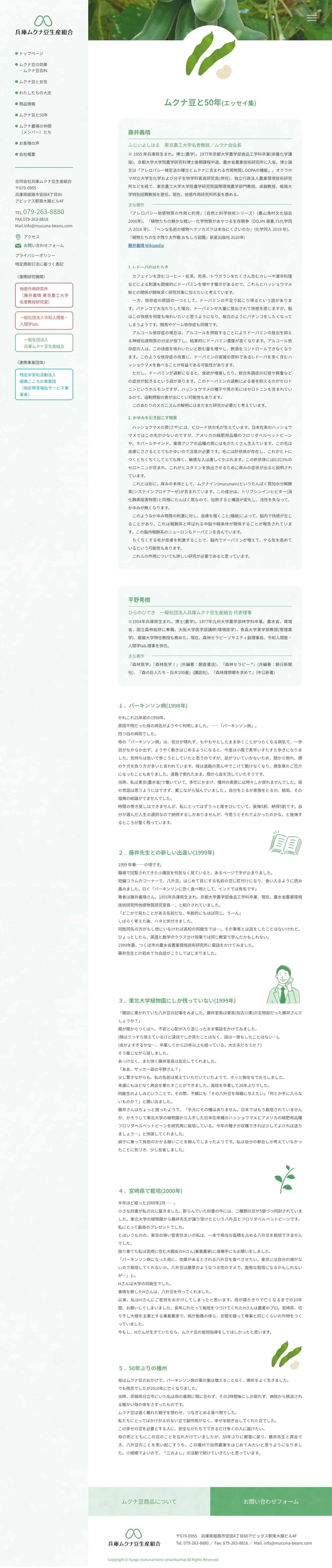10. 植物の視覚
ムクナ豆の蔓は10メートル以上になり、根元直径は500円玉ほどの大きさになる蔓もあります。豆木は1年で枯れてしまいますが、沖縄など暖かい地方では同じ場所で何世代もそのまま自生を繰り返すことができます。
私の専門は林学で、仕事柄多くの巨木と接してきました。かねてより植物には動物と共通する五感――視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚があるのではと感じています。
以下、順に解説していきましょう。
まずは植物がもつ視覚から。
大根やニンジンのへたを小皿の水につけ、窓際に置いておくと、新芽は光の方向に伸びていきます。芽の先端には光センサーのような機能(植物ホルモンのオーキシンによる光屈性)が備わっているのです。
色も識別できます。
その実験は、雑草のスベリヒユ※1を使って行われました。
1990年、ノヴォプランスキー(イスラエル)らはスベリヒユが伸びるその先に、緑や赤、白の小さなブロック(同一プラスチック素材)を置いて、とおせんぼ(通せん坊)をしました。すると、スベリヒユは緑のブロックの手前で、横への枝分かれを少なくし、枝の上方への伸長を優先させたのです。緑のブロックに衝突することなく、避けて生長していきました。
このメカニズムは、植物(スベリヒユ)が光の波長を感知するスイッチをもっているからと考えられています。赤や白には反応せず、緑だけに反応したのは、植物が光の色(波長の組成)を感知する機能をもっていたからで、ぶつからなかったということは、触覚ではない「色を見分ける力」――視覚を持っていたと考えられます。確かに葉っぱと葉っぱはぶつかりませんよね。
そうやって植物は、私たちをも一人ひとり見分けているのかもしれません。
考えてみれば、動物も植物も太陽に左右されるある種のリズム、光のリズムに従いながら生きています。植物の場合は動物に比べて運動のテンポがちょっと遅く、足がないので移動できません。でもじっと一か所にとどまりつつも常時、周囲を見渡しながら次に繰り出す一手を用意しているのです。

※1 スベリヒユは山形では、県民食「ひょう(雹)」として親しまれています。そのゆえんは、江戸時代に上杉鷹山第9代目藩主が倹約のために推奨したからだそうです。