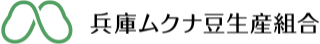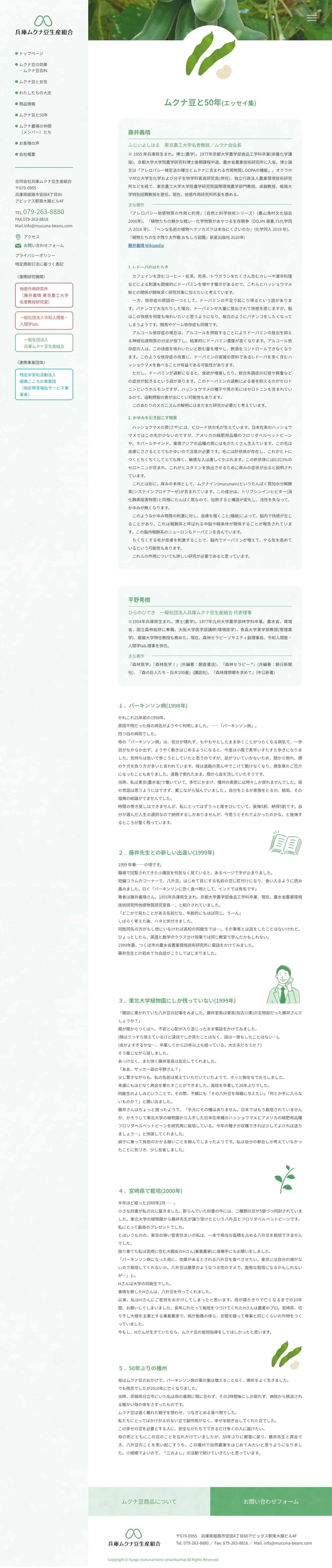17. 『水の戦争』――がぶ飲みするテクノロジー企業
橋本淳司氏が『水の戦争』(文春新書2025.9.20)を公刊しました。
最新水情勢と水資源問題の核心について、「地政学」と「テクノロジー」の視点から知ることができます。橋本氏は、筆者が東京財団にいた時代(2008~13)※1からのご縁ですが、20年に及ぶ同氏の研究蓄積があってこその著作です。
近年、データセンターやAI人気で、冷却用の水需要が急伸しており、TSMC(熊本県菊陽町)やラピダス(北海道千歳市)の登場もあり、改めて資源としての水が注目されています。水需給が逼迫していくことは確実です。
では、次はどうなるのでしょう?
水は領土を超えてやり取りされるようになると、地政学的なテーマになります。
国際河川での水争いは、中東はじめ、インド、中国、タイなどで古くからありますし、2022年、米国アリゾナ州では、サウジアラビア資本が地下水を大量に使用して飼料用植物(アルファルファ)を栽培し、本国へ輸出していることがわかり問題になりました。日本でも農地や森林を外国人(中国)が買い占める動きが活発です。
橋本氏は「土地取得は、地下水や他の自然資源への実質的なアクセス権を伴う行為でもあります。…土地取得は水の支配と直結する問題となりつつあるのです」といい、「問うべきは、資本の国籍よりも、土地の所有形態、そして水へのアクセスが公正に確保されているかどうかという点です」といいます。
同感です。
今の社会は見えづらいのですが、富や資源の偏在が止まらず、①強者である〈投資ファンド〉や〈都心の上級国民〉と、②弱者となった〈小規模自治体〉や〈過疎化住民、意思決定の輪から外された人たち〉の経済力や意識の差が広がっています。
目下のところ、すべてが合法ゆえに厄介なのですが、この格差拡大の動きが水の公正な配分や最低限の生活環境にも影響するようになったとき、後者の取り残されてしまった人たちは、どうすればよいのでしょう?
水は万人にとっての一大事。現代の「地雷」です。