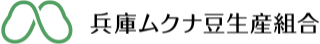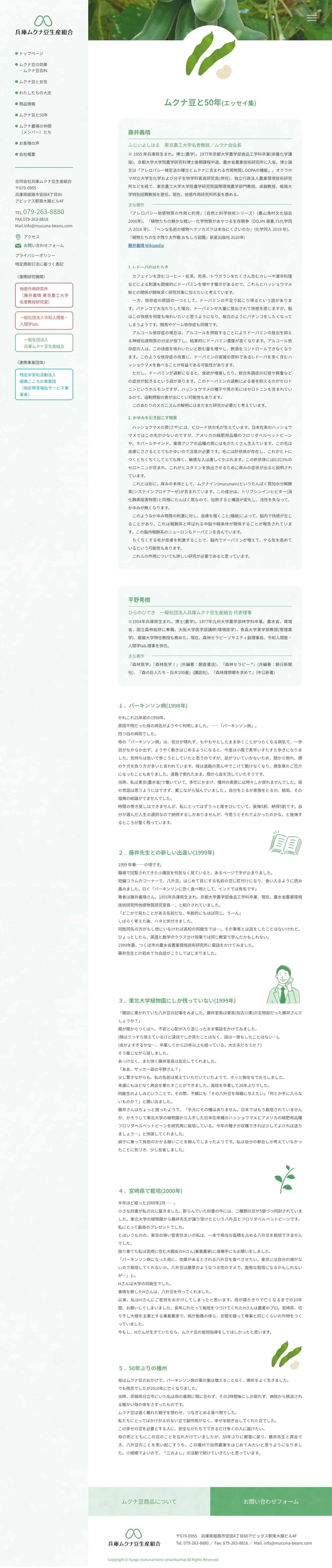19. 植物の知覚力
筆者は創業以来、毎朝ホワイトムクナを6g飲んでいます。私は脳への効果を信じ、ムクナ自身も何か信号のようなものを私へ発しているような気がして、そこで対話が成立しているような気分になります。(科学的でなくて申し訳ありません)
本日誌14 植物の触覚で登場したハエトリグサは、20秒以内に2回刺激されないと閉じません。擬人化していうとハエトリグサは1回目の刺激を20秒間記憶していたことにならないでしょうか?
エンドウマメの巻きひげは、触れてから数分後に支柱に巻き付きはじめます。この場合、エンドウマメは数分間覚えていたことになります。その巻きひげをいったん冷やすと、麻痺してしまったのか巻き付く動きを止めます。でも1時間後に温めたとき、再び巻き付きはじめます。
もちろん、植物に神経システムがあるわけではありません。でもシンプルな記憶装置のようなものをもっていることはまちがいないでしょう。私たちとは違った交信能力と情報処理系のシステムをもっているといえます。光という電磁波に対し、また風や微妙な温度変化を感じとり、蕾を膨らませたり、葉っぱを紅葉させます。動物の各器官と同様の筋肉や神経に似たシステムを植物はもっているのです。
植物の細胞には、①刺激を受けるもの、②信号の役割をはたすもの、③動きをしめすものの3種がありますが、これらはすべての生物に備わっている普遍的な機能です。進化の歴史をたどれば、植物も動物もその祖先は単細胞の生物に行きつくわけですから当然のことかもしれませんね。
植物は大地に根を張り、移動することはないですが、上手に環境に適合しながら、長い目で見ると成育場所を変えながら布域を広げています。植物の五感は動物以上に発達していると思います。