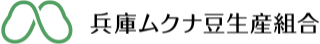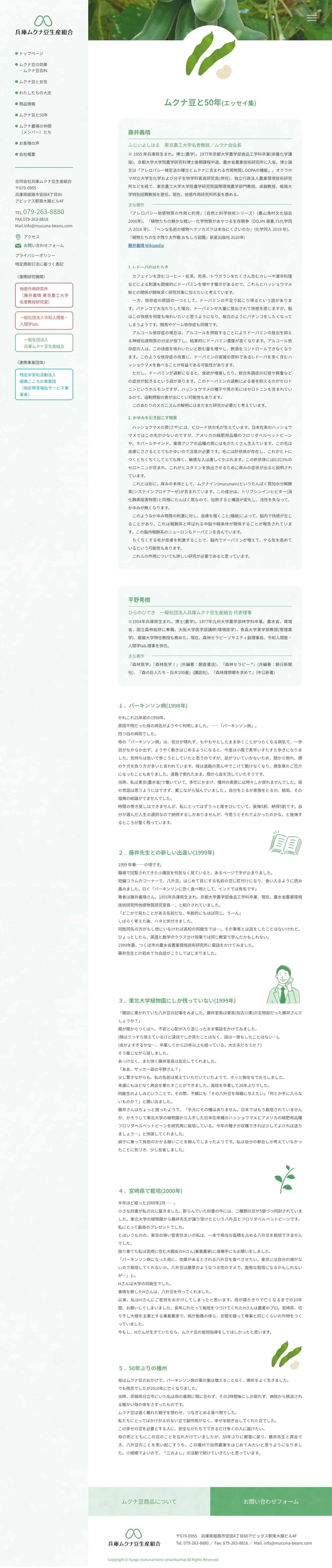3. 藤井先生のムクナ豆
藤井義晴(F)と平野秀樹(H)は同じ高校でした。しかし、一度の会話もなく卒業し、違う道を歩みました。初めて言葉を交わしたのはそれから25年後。二人とも農水省に在籍していたことが縁でした。きっかけは藤井(F)が書いた次の小論です。
忘れられた日本在来の豆 ムクナ
今回は、アレロパシー(植物が本来持っている化学成分による他の植物や昆虫・微生物の抑制あるいは促進作用、他感作用ともいう)が強い植物として約10年間研究してきたムクナについて紹介します。
この植物は、かつてわが国でも、「はっしょうまめ」あるいは「おしゃらくまめ」という名前で栽培されたことがありますが、現在ではほとんど栽培されていません。しかし、やせた土地でも生育し、良い緑肥となること、種子は食用に、茎葉は牧草になり多収であること、繁茂して地表を覆い雑草抑制効果があること、病害虫の被害を受けにくく線虫密度を減らすこと、イネ科植物と共栄関係があること等の特性を持つことから、復活させたいと思います。
ムクナの雑草抑制効果についてブラジルの宮坂四郎先生から教わりました。ムクナは現地でハマスゲやチガヤといった難防除雑草を抑えるのに用いられていました。抑制力の主因は被覆力による光の遮断ですが、アレロパシーの関与も考えられ、調べた結果、特殊なアミノ酸であるL-3,4-ジヒドロキシフェニルアラニン、略してドーパを同定しました。ドーパは葉や根の生体重の約1%も含まれており、広葉雑草の生育を阻害しますがトウモロコシなどのイネ科植物は阻害しません。
ドーパは脳内の神経伝達物質であるドーパミンやアドレナリンの前駆体であり、この性質から、パーキンソン病の特効薬として用いられています。しかし、ドーパが通常の組織中に多量に存在することは稀です。
……ムクナは在来植物で野生に近く、欠点もありますが、今後これらが改善され、熱帯~亜熱帯地方の重要な食糧になることが期待されます。
―― 藤井義晴(農水省農業環境技術研究所)「現代農業」1998.4
パーキンソン病の母をもつ平野(H)が鋭く反応したのは言うまでもありません。
同級生との奇縁に、感謝しています。